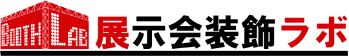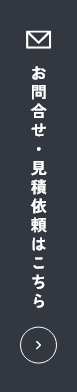何度も展示会出展をしているが、「思ったようにリード数が獲得できない」や「過去のリード数を超えることができない」など、原因のわからないモヤモヤが生じることはないでしょうか。
本記事では、展示会ブースにより多くの来場者を獲得するために必要な、装飾をする上での重要なポイントについて紹介します。
展示会ブースの種類
展示会ブースには異なる4つのレイアウトがあります。
レイアウトの種類は展示会を出展する際の目的や、商品の種類によって特徴が異なります。
次の特徴を正しく理解しないと効果を最大限に発揮することができないので注意が必要です。
商談型ブース
商談型ブースとは、より詳しく時間をかけて商品紹介をすることを目的としたブースです。
そのため、椅子とテーブルを配置したブースになっています。
メリットとしては、商品に興味を持った来場者にとって質問しやすい環境になるため、他のブースと比較しても高い理解度と顧客満足度を獲得することができるのが特徴です。
一方デメリットとしては、椅子とテーブルを配置するためブース内が狭くなってしまいます。
また、来場者にとっても多くの時間を費やしてしまうのではないかと中に入りにくい雰囲気を感じさせてしまうことがあります。
商品展示型ブース
商品展示型ブースとは、実際に商品を展示し、手にとってもらうことで商品イメージを持たせることを目的としたブースです。
メリットとしては、実際に商品を展示しているため、サービスの特徴や価値をわかりやすく伝えることが可能です。また、来場者に実際に体験してもらうことで、不安や疑問点を軽減できることも特徴の一つとなっています。
一方デメリットとしては、コンサルティング業界や人材紹介業界などの無形商材には活用できない点です。これらの業界は他のブースレイアウトを活用する必要があります。
セミナー型ブース
セミナー型ブースとは、一度に多くの人を集めて商品やサービスを紹介しながら具体的に理解してもらうことを目的としたブースです。
メリットとしては、一度の説明で多くの来場者に情報を提供することが可能です。また、同時にスクリーンとマイクを利用するため視覚だけでなく聴覚など五感に訴えて製品の特徴を説明することができます。
一方デメリットとしては、広い範囲の場所を使用するため、小規模の小間数での出展には向いていません。
体験型ブース
体験型ブースとは、来場者に体験してもらうことで商品の魅力や特徴を来場者に訴求することを目的としたブースです。
メリットとしては、商品の特性を直感的に体験してもらえるため来場者にとって商品の利用イメージを持たせやすくなることです。
一方デメリットとしては、体験型ブース自体に大きな費用がかかってしまうことです。また、展示物によっては大きな事故を発生させるリスクも持ち合わせているので注意が必要です。
展示会ブースの種類
展示会で設営されるブースの構造には大きく「木工ブース」と「システムブース」の2種類があります。
しかし、2つの種類があったとしても
「特徴の違いがわからない・・・」
「弊社ではどっちを採用したらいいかわからない・・・」
といった悩みを抱える方は少なくありません。
そんな方へ向けて、「木工ブース」と「システムブース」のそれぞれの特徴からどのような業界に向いているのか解説します。
木工ブース
木工ブースは木材を使って施工されたブースのことを指します。
木工ブースの特徴は以下の通りです。

木工ブースのメリット
- デザインの自由度が高い
木材を使って施工するため、四角いデザインだけでなく曲線などを活用した丸デザインに加工し、他社との差別化を図ることができます。
- カラーリングしやすい
木材を元に装飾をするので、壁紙やシートを貼り付けることが容易です。そのため、コーポレートカラーを活用したブースや目を引くようなブースを作ることができます。
木工ブースのデメリット
- 廃材が多く発生する
基本的に使用された木工ブースは一度きりの使用を想定しているため、展示会が終了した際には多くの廃材が発生してしまいます。
- 価格が高い
デザインに合わせて木材がオリジナルの形に加工されるため、再利用が難しくなります。再利用ができるシステムブースと比較すると価格が高くなる可能性があります。
- 手間と時間がかかる
木工ブースはオリジナルの形に加工する必要があるため、小間数や装飾にもよりますが依頼から完成までは平均的に約3ヶ月程度かかると言われています。
木工ブースがおすすめな企業
展示会で「木工ブース」がおすすめな企業は以下の通りです。
- 他社と被らない独自のブースを作りたい企業
展示会には競合他社が多く出展するため、競合他社に埋もれない工夫をすることが大切です。木工ブースであれば、デザインの自由度が高いのでおすすめです。
- コーポレートカラーを活用したブースを作りたい企業
木工ブースは壁紙やシートを貼り付けることが容易なので、企業カラーだけでなく商品カラーを強くアピールしたブースを作りたい場合におすすめです。
- 満足のいくブースを作りたい企業
システムブースよりも準備期間は長くなってしまいますが、その分制作会社との関係が構築されるため、満足度の高いブースを作ることができます。
システムブース
システムブースはアルミ素材のレンタル部材を使って作るブースのことです。
特にオクタノルムやオメガトラス、マキシマライトなどが有名です。
システムブースの特徴は以下の通りです。

システムブースのメリット
- 価格が低い
システムブースは再利用したものを使い回されるため、安価なものが多いです。
- 設営・解体が簡単
すでにあるシステム部材を組み合わせて作成するため、短い時間で設営が可能です。
また、システム部材はすでに形が決まっているため、新たに素材を作る必要はなく、資材運搬のみで準備が整います。
- 環境に優しい
システム部材は再利用できる部材のため、会期終了後に発生する廃棄物が少なくてすみます。
システムブースのデメリット
- サイズが限定される
システムブースは規定の部材を組み合わせて作るため、木工ブースのようにサイズの大きさを調整することができません。そのため、ブースに合わせて調整をすることも難しいです。
- オリジナリティが出しにくい
システムブースは木工ブースのように独自にアレンジできないため、他社と似たようなデザインになってしまいがちです。そのため、差別化を図ることが難しくなります。
- 部材が汚れている可能性が高い
部材を再利用しているからこそ使用予定の部材に汚れや傷がついている可能性もあります。
向いている企業
- デザインよりも値段を重視したい企業
初めての展示会出展でまずは低い値段で出展してみたいと考えている場合は、あらかじめデザインが決まっていて設営しやすいシステムブースが良いでしょう。
- 何度も展示会に出展する企業
PRしたい商品やサービスが変わらず、短い期間で数多く展示会に出展する場合は、ブースデザインを再利用できるシステムブースがおすすめです。
リード数を上げる展示会ブースデザイン
ブースレイアウト・デザインについては理解が深まりましたか?
ここからは、レイアウト・デザインを踏まえてさらに展示会にてリード数を上げるためのコツを紹介します。
- 一目で理解できるようなブースになっているか
展示会の会場は広いだけでなく、多くの競合が出展しています。そんな中から来場者に注目してもらうためには一瞬見ただけでも理解できるようなデザインにすることが前提となります。
例えば、「商品の良さを伝えすぎて情報量が多くなっていないか」や「装飾が派手になりすぎていないか」など来場者の目線に立ってレイアウトを考えることが必要です。
人間の第一印象は3秒で決まると言われてます。そのためブースの第一印象によって集客率も変化していくので意識することが大切です。
- 来場者が興味を引くような工夫が施されているか
多くの来場者はブースの中に入ってくることは少ないです。まずはこの事実を認識しましょう。
展示会を訪れた来場者の大半は、どのような商品・サービスがあるのかを知りたいと考えています。特に、興味あるものに時間を費やしたいと考えています。そんなとき展示物がブースの一番目立つ場所に置いてあったら来場者は自分にとって必要なものかどうか瞬時に理解できます。コンサルやIT系のように無形商材の場合は、動画を活用するのも効果的です。
- 魅力を最大限活かせた小間位置にあるか
小間の位置によってブースのデザインは大きく左右されます。
例えば、ブースの開放面はどのくらいあるのか?や入り口やトイレ・休憩スペースなど比較的人の集まりやすい場所を確保できているか?など来場者にとって目につきやすい場所を選ぶのがポイントです。
さらに、来場者が興味をもったタイミングで、ブースに入れるような仕掛けをしておくと良いでしょう。
展示会ブースで気をつけること
- 過度な装飾による情報過多
ブースの装飾は控えめに、情報は必要最低限にすることが大切です。
過度な装飾や情報を埋め込みすぎると来場者にとって「何を伝えたいブースなのか」「どんなベネフィットがある企業なのか」を判断することができなくなってしまいます。
来場者の混乱を防ぐためにも、展示する商品を厳選しシンプルな装飾をすることを意識しましょう。
- コンセプトの明確化
コンセプトは一言でまとめられるものにしましょう。
コンセプトを明確にすることで、来場者がスムーズにブースに入るかどうかを決定することができます。
また、コンセプトをあらかじめ決めておくと、そのコンセプトにあったブースデザインを決めることができるので、準備もスムーズに行うことができます。
- ブース周りの確認
ブース周りはブースの顔とも言われています。
そのため、ブース周りで来場者がブース内に入るかどうか判断する場合があります。
例えば、ブース外の通路際にこれといった目玉商品をが置いていなかったら来場者はどのような行動を取るでしょうか?他にも、ブース前に声掛けもせずに立っている出展者がいたら来場者はどう感じるでしょうか?きっと、来場者は足を止めてくれることはないでしょう。
まずは明るく、印象に残りやすい配色を心がけ、ブース内に入らなくても伝えたいことがわかるようなレイアウトがおすすめです。
まとめ
今回は展示ブースの種類についての基本的な知識から、集客力が上がる装飾の特徴、注意点まで幅広く解説しました。
ぜひこれらのポイントを活かして効果的な展示ブース装飾に役立ててください。
なお、展示会ブース装飾について気になることがございましたら、以下からお気軽にご相談お待ちしております。